▼はじめにご挨拶
(自己紹介等が煩わしい方は、下までスクロール下さいませ。)
お初にお目にかかります。"重力魔剣士ジェイル"を執筆しております、奈下西こまと申します。元々は音楽活動を中心に芸術をしていたのですが、恥ずかしながら収入がなく、このままではのたれ死んでしまうと、まずはまともな職探しと思い立ったのですが、私はとことん仕事というものに縁がないらしく、繰り返されるパワハラ、嫌がらせ、不当解雇や給料未払いにより、元来虚弱な精神状態が更にガタガタになってしまいました。創作活動を行うこと、ひいては生き続ける気力自体が、徐々に奪われつつあります。
それでも、私は自分の作品は、世界で唯一私にしか創造出来ない物であると自負しております。そう信じた上で、残った気力を総動員させ、”重力魔剣士ジェイル”の執筆を進行させております。
そしてこれらの作品を広く世の中に知らせることで、真摯に生きようとする故に損な役回りを受けさせられ、それでも尚、戦い続ける人々の支えとなれればと心より切望しております。
それだけが、僕がこの世に生まれて来た理由であり、無意味な僕の生を価値あるものに変える唯一の方法だと心より信じております。さもなくば、僕は即刻この世から消えねばなりません。
何卒、このプロジェクト要綱を最後までお目通しいただきたいとお願いを申し上げます。
▼このプロジェクトで実現したいこと
活動費と銘打っておりますが、本当の意味は少し違います。私が果たせていない、本当に大変な、"社会人として働く"という役割を果たしておられるであろうあなた方にとって、私の魂を込めて紡いだ作品は、お金を出すだけの価値があるのか、ないのか。
奈下西こまという人間に、投資する価値があるのかないのか。
私の作品の一部をご覧頂いた上で、その審判を下していただきたいのです。
▼これまでの活動
ネット上で同名義にて作詞作曲演奏歌唱活動(継続中)
▼資金の使い道
小説、"重力魔剣士ジェイル"の執筆活動費用として。作品の完成は2019年末を予定しておりますが、前後することがございます。
未定ですが、みなさまの支援額の如何によっては自費出版や法人設立等も視野に入れております。
▼リターンについて
感謝の思いを込めた自筆の手紙をお送りすることに加え、今回執筆している小説だけに関わらず、この先に発表する私の作品内の人物名、戦技名、地名、施設名、組織名等、固有名詞の命名をしていただけます。性別が合えばご本人の名前をそのまま使用することも可能と思われます。とても良い記念になるのではないでしょうか。
(事前に念入りに協議させて頂きます。もしも作品の雰囲気にあまりにも符合しないような場合は再協議を行います。監修は奈下西こまが行うものとします。今回の作品は西洋風ダークファンタジーですが、将来は日本の学園モノも執筆する予定です)
▼最後に
ここまでご覧頂き誠にありがとうございます。本当に、これだけでも幸いです。
本来であれば世界で誰一人、僕の作品を支持してくれなくても、転がる石のように戦い続け、摩耗し切って力尽きたならば、潔く自決するべきであることは重々承知しております。
しかし余りに弱い私は、あなた方の善意に、自分の人生の在り方を委ねようと、そう考えてしまいました。どうかお許しください。
それでは前置きが長くなってしまいましたが、”重力魔剣士ジェイル”の世界をご覧下さい。
▼作品概要
時代は現代よりはるか未来、 原因不明の厄災により文明は滅びました。
残された人々は、 世界を蹂躙するオルディウムと呼ばれる怪物たちに怯えながらも、 文明を再構築しながら逞しく生きています。
主人公は、ジェイル=クロックフォード、35歳の双剣使いの大男 です。彼は15年前に恋人を惨殺されました。 その仇を根絶やしにするため、相棒のアリアと旅をしています。
それら仇の正体は、旧文明が滅びた原因となった、”祟り神” と呼ばれる少女の肉体を依代に開発された古代兵器たちです。
ジェイルとかつての恋人は当時の国王に謀られ、 封印されていたそれらを解き放ってしまったのでした。
ジェイルの相棒のアリアもまた、”祟り神”の一柱ですが、 彼らの創造主の寵愛を受けていた彼女は、他の”祟り神” に妬まれ、 封印中に寄ってたかって半壊の憂き目に合わされていました。
恋人が惨たらしく殺害され、”祟り神”たちが各地に去った後、 ジェイルが死の淵で絶望を撒き散らした結果、 生物の負の感情を糧にする、”祟り神” の性質により復活したアリアは、蘇生したジェイルに自らの能力” 重力を操る力”を分け与え、共に復讐することを誓ったのでした。
▼登場人物解説
ジェイル=クロックフォード
35歳、小太刀二刀流の大男。15年前、 恋人を失ってからずっと生きることに罪悪感を抱え続けているが、 仇討ちに心血を注ぐことで生きる目的としている。
アリア
?歳、銀髪赤眼、見かけは十代前半の少女。 かつて文明を滅ぼす使命を負った人型兵器、祟り神の一柱。 ジェイルを自分の神子とし、能力を分け与えて彼に協力している。
オルディウム
文明が滅ぶ前後に現れたとされる怪物たち。詳細は不明だが、 既存の動物から急速に進化したとされ、 現在多くの種族が確認されている。例外なく、 獲物を可能な限り苦しませてから喰い殺す性質がある。
ラーズ
27歳、傭兵部隊を率いる。少数精鋭で様々な戦果を挙げ、 今回アトラス国王よりオルディウム討伐の勅命が下った。 頭に血が上りやすいタイプでまだ成熟には程遠いが、 仲間にも恵まれ、その実力は確かなもの。
ルチル
年齢不詳、見かけは十代後半の少女。ブラウンエルフの亜人種で、 ラーズ隊所属の高位魔術師。 家族の仇であるオルディウムに執着し、その起源を追う。
サーシャ
21歳、ラーズ隊最年少の女弓兵。 思ったことをすぐ口にする生意気なタイプだが、 類稀なる弓の才能を持ち、その実力は国でもトップクラス。
ヒューズ
29歳、影の薄い十字槍使いの男。ラーズとは旧知の仲で、 その槍の腕でラーズと共に数々の修羅場を切り抜けて来た。 表には出さないが、今回の勅命で成果を挙げ、 国に召し抱えられたいと思っている。
◆本文より抜粋、戦闘シーン①
弓兵サーシャ vs. 大型猛禽類オルディウム
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その瞬間、感情はただの足枷となる。
もしも外したらどうしよう、 獲物が動いたらどうしようという類の心配は、 考えるだけ全く無意味なことだ。 今までに気の遠くなるほど繰り返して来たように、ただ、 中たるように射る。
それだけで、すべては解決する。
サーシャの一家はアトラス東部に広がる森林の集落で、 綿鴨を狩って生計を立てている。
サーシャが初めて獲物を狩ったのは、7歳の頃。
その得物は、師でもある彼女の父が、 イチイの木を削り出して設えた張力10キロの弓だ。
これは成人ならば問題なく引ける重さだが、 小さな子供には明らかに不釣り合いな代物。
それを彼女に与える父も父だが、 なんとサーシャはそれを苦もなく引き切り、 たった2日の訓練の後に、見事に綿鴨を射抜いた。
もっとも、彼女の一撃だけでは流石に仕留めきれず、 父が直後にとどめを刺したのだが、その見事な結果に、 普段は寡黙な父も大層喜んだという。
何代にも渡って猟師として生きてきたサーシャの一族には、 生まれながらにして非凡な弓の才能が備わっていた。それは、 進化と言って差し支えのないほどに。
しかしサーシャは、女なんだからもう弓は止めろという、 一部の親戚の心ない声に嫌気が差し、 女でも男よりも優位に立てると証明する為、 数年前から単独で傭兵を生業として生き始める。
そしてある任務にまつわる縁から、 ラーズ隊へ厄介になることになったのだった。
サーシャとルチルは、 靴を脱いで素足になった上で細心の注意を払い、 木の陰に隠れながら、 目標地点までおよそ200メートルまで慎重に近付く。 そこまで視力の良くないルチルにも、 木々の隙間の向こうに聳える、巨大な黒い塊を確認出来た。 標的たちは折り重なって眠っているらしく、ほぼ動きがない。 サーシャにとって、単に命中させるだけならば容易い距離だが、 複数の強大な怪物相手となると、 強化魔術で補強した鏃で急所を正確に射たとしても、 表層を貫けるかどうか怪しい。
そこでギリギリの所まで、 慎重の上にも慎重を期して距離を詰めていく訳だが、 これ以上は危険だという共通の感覚が、 二人の胸中に俄かに迫り上がる。 標的までの距離はおよそ150メートル。
ルチルが目で合図を送り、無言で高位迷彩術式を展開する。 光を屈折させ捻じ曲げることで、 ゆっくりとした徒歩の速さでしか移動出来ない事、 効果持続時間が最長3分程度という条件はあるが、 二人の存在は最早、何者にも感知不能である。二人は尚も、 ゆっくりと標的たちに近付いていく。
ここまで来れば、ルチルの目にもはっきりと標的が見て取れる。 この距離でも相当な迫力だ。
幾度となく死線を潜って来た二人であったが、 これ程までの緊張は味わった事がなかった。 ルチルの首筋を冷や汗が伝う。
距離およそ50メートル。 森林がちょうど開けた空間に彼等はいた。
目標の群は、やはり眠っているらしい。これは思わぬ僥倖だ。
その周囲には哺乳類の毛や衣服の一部が散乱し、 夥しい量の血痕が残されていた。
サーシャ達の位置から確認出来るオルディウムは、4体のみ。 しかしいずれも頭部か首筋を露出している。
──この距離ならば、抜ける。
そう確信したサーシャは、先行するルチルの肩にそっと手を置き、 木の陰にしゃがませる。
そしてサーシャは数秒の内に呼吸を整える。
中てると決意した瞬間、感情はただの足枷となる。
外したらどうしよう、獲物が動いたらどうしよう、 それらは考えても意味がないこと。
ならば、ただ外さないよう射る。
それだけで、全ては解決する。
そして流れるような動きで、矢を番え、弦を引き絞った時。
もう彼女は、何も、考えていない。
黒い強弓から放たれた最初の矢は、ほぼ直線の軌道を描きながら、 木々の隙間を切り裂き、 サーシャから見て一番遠い地点で眠っていたオルディウムの左瞼ご と眼球を貫通し、脳を損傷した。
トリカブトの毒は、生物の呼吸器に特に重篤な作用を及ぼすので、 仮に即死を免れたとしてもそれがダメ押しとなるに違いない。
続いて、最初の矢が着弾するよりも早く放たれた矢は、 サーシャから二番目に遠い位置にいた若いオスのオルディウムの首 筋へと吸い込まれる。
またも驚異的な精度で硬い羽毛部分を避け、なおかつ矢尻部分を、 動脈まで穿孔させることに成功した。 後は麻痺するのを待つだけで比較的簡単に仕留められるだろう。
いかに狩られる事に慣れていないオルディウムとは言えど、 本能的に危機を察したメスの個体が警戒の声を上げようと嘴を開い たその時、3本目の矢が口内を貫き脳へと至る。
苦痛の声を上げ、激しくのたうち始める同胞たち。
最後のオルディウムはもう完全に襲撃者の存在に気が付いている。 はっきりと知覚出来た風切音。
これは人間の弓兵の仕業だ。
すべてのオルディウムに共通することであるが、 異常なほど旺盛な攻撃性と加虐性の他、 種族によって違いはあるものの、 それぞれの進化元の生物よりも高度な知性を持ち合わせている事が 多く、これがオルディウムの脅威に拍車を掛けている。
最後のオルディウムは全身を瞬時に強張らせ、 逆立った羽毛と強靭な筋肉で、全身を守る鎧を形成した後、 その驚異の視力で、矢が飛んできた方向を索敵する。
しかし肉眼で3キロ先の兎も正確に探し出す筈の眼は、 襲撃者の姿を捉える事が出来ない。
彼がその不自然さに気付いたその直後。
言葉を持たない彼の最期の思考を、無理矢理に言葉で表現すると、 こうなる。
"なんだこの黒い点は?大きく、大きくなる…"
サーシャがオルディウムに向けて放った一撃は、 彼の眼球の中心を、恐るべき精度で捉えた事で、 その距離感を掴みにくくし、彼に回避行動を起こさせなかった。
特製の鏃は、 初めの1匹と同じように彼の眼球の中心を抜けて脳に到達、 同時に大量の毒液を溢れさせながら静止した。
◆本文より抜粋、戦闘シーン②
"神降ろし"ジェイル vs. 超大型オルディウム・フォルス
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その表情は、ルチルが知っている、 いつも穏やかに微笑んでいる少女の面影は一切なく、 見る者の本能に強烈な【死】を想起させる、 原始的で正体不明の恐ろしさを湛えていた。
そうして、アリアは大きく息を吸ってから、 感情の一切込められていない冷え切った声で、 歌うように唱え始める。
"天に坐す我等が王の御名において、我治め司りし力、 此度の縁の舫を辿り、我が神子に顕現せしめる也
我が神子ジェイル=クロックフォード、我、第十三荒御霊アリア= リリウムワイズの神兵となりて、諸々の禍事、仇成す者共、 灰燼に帰し討ち祓うべし
来たれ神劔、神子に呼応し一切凡ての厄災を断ち
来たれ蟲鎧、羸弱なる神子を庇護せしめよ
罪穢れに満ちたる人の子ら、等しく無に帰すべし"
ルチルの位置からでは到底、 アリアがどんな術式を発動させたのか聞き取れなかったが、 それが極めて異質、かつ重大なものであることは理解出来た。
しかし、そんな恐ろしい光景を目の当たりにしても、 ルチルは目を逸らす事が出来ずにいる。
双眼鏡を握り締める手は硬直し、両の瞳は決して閉じられず、 まるで魅入られたかの様に、一心にアリア達を見つめる。
やがて、アリアの胸元の闇が分散しながら虚空を移動し、 ジェイルの全身を覆い尽くす。
それは彼が黒い霧に食われている様に見えた。
があああああ!!
瞬間、屈強なジェイルが苦痛に耐えられず声を上げる。
黒い霧は、ジェイルの全身をくまなく包むように浸透すると、 無数の杭を生成して彼の全身の骨に食い込み固着し、 実体化していく。
その際にジェイルが受ける苦痛は、 炎に全身を焼かれるのに等しいものだった。
そして彼の装着していた簡素な板鎧とは全く違う、 ぬらぬらとした生物的な艶と質感を持った、 全身を覆う装甲が現れる。
それは例えるならムカデや蜘蛛を無理矢理、 人型に変形させた様な、生理的な嫌悪を引き起こす姿であった。
彼が腰に差した双剣も、 同様に鈍く赤黒く光る金属に変質している。
「....」
変貌したジェイルは無言で黒い双剣を抜くと、 肩の力をだらりと抜き、微かに前傾姿勢の構えを取る。
同時に、レイラもほぼ同じ方法で儀式を実行し、 相棒の超大型オルディウム、フォルスに何らかの変化を起こす。 しかし、その見た目には特別な変化はなかった。
「人間の様な脆いものを選ぶから、 肉体の強化自体にも力を割くことになる。極めて非効率だ。 その選択、後悔するぞ?」
レイラは勝ち誇った様な笑みでアリアへ言い放つ。
その表情を見たアリアは、何処か哀しそうな表情で返答する。
「レイラ、思えばお前とは長い仲だったな。どちらが勝っても、 恨みっこ無しだぞ。さあ、白黒を付けようか」
──ギン!
その時、 アリアの台詞に合わせたかのように突如として虚空から現れた、 青白い光の格子で出来た球体が、アリアとレイラを同時、 そして瞬時に拘束する。
高さおよそ2メートル程の光の球体は、二人を内部に拘束、 取り込んだまま地上から数メートルの高さまで、 ゆっくりと浮かび上がる。間もなく始まる、 異形同士の死闘を見守る為に。
「…」
その死闘を見守るルチルは、 辛うじて声を上げることはなかったが、 現実離れしたその有り様に、動揺を隠せない。
兵器。
ジェイルはそう言ったが、 この戦闘は現代の兵器を用いたそれの特徴には全く当てはまらない 。
これは、どちらかと言えば魔術の領域。
しかし、双眼鏡越しの有様は、魔術と断ずるにも不自然だった。 これ程までに、禍々しい術式は、 高い練度で魔術を修めたルチルにとっても、未知のものだった。
──否。必死で記憶を手繰り寄せていたルチルは、 突如としてハッと気が付く。
この瞬間まで完全に忘却していた事だが、 彼女には薄っすらと心当たりがあった。
それは二十数年前、彼女がまだ幼かった頃。
一人目の師でもあった父の書斎にあった、所々落丁しているほど、 古ぼけた書物。失われた歴史の伝承。この星を襲った厄災の顛末。
目を輝かせて表紙を眺める幼い日のルチルに、 生前の父は窘めるように言っていた。 この書物は一族に伝わっては来たものの、 今の文化から考察すれば眉唾で、 取るに足らない与太話に違いないと。
しかし幼い頃の彼女は、その恐ろしい物語に妙に引き込まれ、 読めない字や、理解出来ない表現の意味を父に尋ねながら、 何度も読み返したのだった。
厄災の起こる直前の世に、かつて君臨した絶対的な王が、 ある目的の為に生み出した兵器の総称。 昨晩ジェイルの話を聞いた時にはすぐに結びつかなかったが、 それをあの書物ではこう表現していた。
【祟り神】と。
そして、それらの兵器はそれぞれ、 この世界を構成する様々な力を司り、自在に使役したと。
ルチルは尚も思考を続ける。
もしもアリア達がそれと関係があるなら、魔術と似て非なる、 あの不可解で独特な術式も頷ける。そして、 父があの古文書を創作だと断じたのも、 魔術を深い領域まで修めた彼だからこそ、 想像すらつかなかったからだろう。
──変貌したジェイルが、 およそ十メートルは開いていた間合いを、 地面が抉れる程の驚異の鋭さの踏み込みで瞬時に詰める。
狙いは超大型オルディウム、フォルスの脚だ。
しかし同等の儀式によって、 感覚器官を大幅に強化されたフォルスは、 その巨体に見合わぬ素早い反応で、ジェイルの身体の軌道上に、 右の翼を合わせて、力任せに薙ぎ払う。
バキャッ!
凄まじい音と共に炸裂した一撃で、 ジェイルが踏み込みの方向と真反対へ吹き飛ぶ。
呆気なく決着かと思われたが、 彼が地面に叩き付けられる事はなく、空中で急減速したと見るや、 そのまま体勢を整え、何事もなかったかのように着地する。
──通常であれば絶対に起こりえない、 慣性の法則を完全に無視した動きだ。
「小癪な。あの領域までお前の力を使えるか。しかも――」
レイラの視線の先にあるのは、 青い鮮血で一部を染められたフォルスの翼。インパクトの瞬間、 ジェイルのカウンターの一撃が、接触個所を切り裂いていた。
「レイラ、神子を丹念に育てたのはお前だけじゃない。 ゼルにはそれだけの理由があった。十五年間ずっと…文字通り、 血反吐を吐きながらわたしの力と同調してきたんだ」
家族の死後、ルチルが新たに身に付けた能力の内、 一番のウエイトを占める要素は、新たな魔術の獲得でも、 魔術使用回数を伸ばす為の精神力の強化でもない。
"手練れであった筈の父の油断のせいで、 家族全員が命を落とした。"
この事実は、彼女を永らく苦しめた。結果、 彼女は自身を律するルールを定めるに至る。
──決して既知の敵に対して油断せず、 未知の敵に対しては早急に性質を見極め、 この私が主体で突破口を作る。
その確固たる決意と、 ラーズの部隊員として積み重ねて来た経験が、 双眼鏡越しの未知の戦闘を解析、推測する。
彼らが使役する、世界を構成する力とは、 おそらく火の力や雷の力等、 魔術と共通する属性エネルギーに違いない。
だとすると、 今ジェイルが対峙しているレイラと呼ばれた少女と巨大なオルディ ウムは、空気、 若しくは風に関係する力を自在に扱えると見て良い。
巨大なオルディウムを使役している様に見える、 正体不明の少女は、激しい暴風と共に突如現れ、 ジェイルの渾身の斬撃をふわりと、まるで風に乗る様に躱した。
──ジェイルは、ゆっくりと立ち上がると、 やはり双剣を握った両腕をだらりと脱力させ、前傾姿勢になる。
そして先程と同じく、 膝の抜きを利用した独特の蹴り出しで瞬時に最高速まで加速、 怪鳥フォルスへと再度肉薄する。
外骨格とでも言うべき鎧に、陽光が反射し鈍く輝く。
相当の手練れであっても目で追えない程の、斬撃に次ぐ斬撃。 それらは先程よりも明らかに速度を増している。
黒い影が怪鳥の周囲を縦横無尽に舞う。
フォルスもまた、 その巨大な身体からは考えられないほどの速度のカウンターで応戦 するが、先程とは違い、ジェイルの速度に僅かに届かず、 やがて少しずつ全身の羽毛が、青い血で濡れ始める。
やがてフォルスの巨大な嘴が、ジェイルの残像を虚しく貫いた時、 ジェイルの実体は怪鳥の頭部の真後ろの頸部に飛び乗っていた。
間髪入れず、 小太刀を握った右腕を自身の左頬に付けんばかりに振りかぶり、 必殺の一撃をフォルスの後頭部へ放つ。
しかしその刹那、ジェイルの斬撃が、見えない壁に阻まれ止まる。
手に汗を握りながら双眼鏡越しに見守るルチルが、 怪訝な顔を浮かべた時、 その何もない筈の空間が轟音と共に弾けた。
ズドン!
極限まで圧縮された空気の塊がジェイルのゼロ距離で炸裂し、 ジェイルの身体が宙に舞う。
「調子に乗るな、人間風情が」
状況を逆転する一撃が見事に決まり、したり顔でレイラが言う。
ジェイルの身体はだらりと脱力した状態で、 フォルスの頭部の高さから更に10メートル程、 錐揉み飛行で斜めに上昇した後、 頭部から真っ逆様に落下していく。
そして、そのまま地面に激突するかに見えたその瞬間、 またもや慣性の法則を無視したような動きで、 身体を半回転させて体勢を整え、ほぼ無音で着地に成功する。
「こざかしい...」
レイアはそれを目の当たりにして、 怨みがましい表情を隠そうともせず、ジェイルを睨め付ける。
黒い外骨格を纏ったジェイルの回避の動作は、やはり異常で、 ルチルは、まるでジェイルは自分の体重を忘れたようだ、と思う。
"体重を、忘れる"
自分自身の考えに、ルチルはハッと気付く。
少女らの能力は先述の通りでほぼ間違いなかったが、 対するジェイルの能力はずっと見当が付かなかった。 しかしここでルチルは、ようやく結論に至る。
ジェイルは、"自身の重さを自在に変えられる能力"を駆使して戦 っていると。
ジェイルの二度に渡る、不自然極まりない着地のプロセス。 その原理としては、空中で自重を極端に軽く変化させ、 運動エネルギーを激減させる。 すると作用が増した空気抵抗でほぼ落下速度が0になり、 無傷で着地することが出来る、というものに違いない。それは、 蟻がどれほど高所から落下しても、 決して致命傷を負わないように。
不自然と言えば、彼が刃物が通じない筈の鎧竜や、 巨大な猛禽類の頸椎を、苦もなく切り刻んだ事にも、 ジェイルの能力がもしそうだとすれば、合点が行く。
ジェイルはおそらく、斬撃のインパクトの瞬間だけ、 自分の質量を劇的に増す事で、 超人的な威力の斬撃を繰り出している。
しかし、敵自体の重さや、 身体に触れていない物体の重さを変えることは不可能なのだろうと いうことを、ルチルは今までの彼の戦闘に鑑みて結論付けた。
──ジェイルがまたも刀を携え、 傷だらけのフォルスとのかなり開いた間合いを三度詰めようとした その時。ジェイルの膝が突如、ガクッと落ちる。
「脳震盪か」
アリアが無表情で呟く。
アリアの未知の術式で、 全身を強固な鎧に包まれたジェイルであるが、 頭部は視覚や聴覚を遮断する訳にはいかず、 装甲の隙間から侵入した爆風が、 僅かではあるがジェイルの脳に損傷を与えていた。
「好機」
レイラが凶悪な笑みを浮かべ、呟く。
フォルスがそれに呼応し、その巨体を突進させようとする。
ジェイルは苦し紛れに、左の膝を突いたまま、 右手で小太刀を背に担ぐ様に構え、 そのままフォルスの頭部目掛けて投擲する。
しかし、脳震盪の影響か、右手からすっぽ抜けた小太刀は、 その狙いを大きく逸れジェイルから見て遥か右側へ飛んで行く。
レイラとフォルスにとっては、好機に次ぐ好機。――だが。
「見事に謀れた、そう思ったか?」
言葉を発したレイラの表情は、一瞬前とは打って変わり、 極めて冷静だった。
フォルスの左首筋の辺りで、 見当違いの方向へ飛んでいった筈のジェイルの小太刀が、 見えない壁に阻まれ静止している。
「人間の神子よ、私はお前の力を見誤っていた。だから、 先程は追い詰められた。今こそ認めよう、私は間違っていた。 そして、お前ほどの手練れがこの局面で、 こんな悪手を打つ筈がないのだ」
ジェイルの掌から伸びた、 外骨格と同じ色の太さ1センチほどのワイヤーが、 空中で静止している小太刀の柄頭へ真っ直ぐに伸びている。
ジェイルは、わざと小太刀を投げ損じた様に見せ、 外骨格の能力を密かに発動させ、 モーニングスターや鎖分銅の要領で、 フォルスの頸動脈を狙撃したのだった。
ジェイルの必殺の一撃が完璧に防がれた様を目の当たりにし、 茫然としたルチルは、(ああ、 だからあの鎧は虫みたいな気持ち悪い見た目なんだな) と現実逃避気味な事を、意識の外で考えていた。
フォルスが風の防壁をかき消すと、 ジェイルの小太刀が重力に従って落下し、 フォルスの足元に落ちる。
「流石はアリアの神子だ。惜しかったぞ」
レイラがそう言うと、必殺の一撃が不発に終わり、 片膝を突いたままのジェイルの至近距離で無数の圧縮空気が炸裂す る。
ジェイルは防御に邪魔な左手の刀を瞬時に納刀し、 両の腕で急所を防御するが、それだけで防ぎ切れるほど、 甘い火力ではない。
「…!」
声を上げそうになるのを左手で必死に抑えながら、 ルチルは涙目でなおも見守り続ける。
ジェイルの身体は爆風で後方に吹き飛ばされ、大の字で空を仰ぐ。
装甲は所々剥がれ、生身の部分からはことごとく出血している。 そしてそのままの体勢で微動だにせず、完全に沈黙した。
しかしその表情は、未だ健在の兜に隠され、 伺い知ることは出来ない。
フォルスもまた、血塗れの巨体を引き摺るように、 地響きを立てながらジェイルへ近付く。
そしてジェイルを足と足の間に挟むように立つと、 身体を天へ仰け反らせ、その巨体に見合う凶悪な咆哮を轟かせた。
──勝鬨だ。
そして決闘の敗者の末路は、定まっている。
フォルスはその巨大な嘴で、敗者に引導を渡そうと、 頭部を高く天に振り被る。
その時。
死に体に見えたジェイルが間隙を突き、残った右腰の小太刀を、 仰向けの状態とは思えない速度で抜刀する。 常人では考えられないほど発達した脊柱起立筋があってこその芸当 だ。
そして、そのままの速度でほぼ真上に位置する、 フォルスの頭部目掛けて投擲。フォルスは頭部を振り被った事で、 真下にいるジェイルは完全に死角に入っている。
凄まじい速さで放たれた小太刀の切っ先が、 フォルスの頭部を斜め方向に串刺しにする直前。
フォルスはまるで下顎に目が付いているかの様な超反応で、 頭部を左方向へ素早く振る事で死の刃から逃れる。
「――全く、油断も隙もないやつだ」
レイラは口の片側を吊り上げ、心底嬉しそうに呟く。
「今のは本当に危なかった。流石はアリアとその神子、 と言ったところか」
万策尽きたジェイルは、 あろうことか反射的に腕で顔を守るような防御反応を取ってしまう 。
それは武とは程遠い、虐げられる弱者の、命乞いの所作。
その様子を見て、 オルディウムとしての本能を大いに刺激されたフォルスは、 にわかに眼を血走らせ、ズドンという地響きと共に、 ジェイルの腕を荒く踏み付ける。
「…ぐっ!」
ジェイルが苦痛の声を漏らす。
外骨格の強度により辛うじて千切れず、骨折だけで済んだものの、 ジェイルの身体は完全に地に磔にされてしまった。
最後の悪あがきが徒労に終わったと知ったルチルの頬に、 大粒の涙が伝い始める。
彼女の祈りは届かなかった。そう絶望した彼女は、 ここで遂に見守る事を止めてしまう。
「はは!これ程の逸材でも命乞いか。所詮は人間、 呆気ないものだ。だが、アリア。ここから先は恨みっこ無し、 そう言ったよな?」
「そうだ。レイラ、これでお前とも今生のお別れなのは、 わたしも結構、本気で残念に思っているんだ」
圧倒的に不利な立場の筈の、アリアの含みを持たせた台詞。 強がりではない。こいつは、決してそんな性格では、ない!
「フォルス!」
悲痛な叫びが響く。
視線を戻したレイラの目に飛び込んで来たのは、 相変わらず空を仰ぐジェイルの上半身に、 青い液体が滝のように降り注いでいる光景。
それは石像のごとく、 硬直したフォルスの頭部を上下に刺し貫くように穿たれた傷から、 一定のリズムに合わせて止め処なく溢れる、青い血。
「ああああ…馬鹿な!…なぜ…なぜだ…!」
勝敗が決したのを目の当たりにして、 レイラはうわ言のようにに繰り返す。
アリアは、何も語らない。 至極当然の結果だとその表情が語っている。
「投げた刀を…フォルスが避けることも、 すべて織込み済みだったのか…」
レイラは、悲しげな表情を隠すことなく俯いたまま、独白する。
「いや、そもそも一度目の投擲も当てる気がなかった…生成した縄 の太さを、印象付けるために…あれすらも、 布石に過ぎなかったのか…」
「さっきお前は、ゼルを侮るのは止めたと言ったな。 その台詞を聞いた時点で、こっちの勝ちを確信したぞ」
押し黙るレイラに、アリアは続ける。
「根本的に違う存在であるものに抱いた認識を、 そう簡単に変えられるものか。刃物を持った人間が、 子猫に対して油断せずに戦うと口で言ってみても、 意識まではそうはいかない」
レイラはぎりりと奥歯を食い縛る。目に浮かぶのは、紛れもない、 絶望。
「蠱鎧で作れる糸の強度は、麻糸と同程度だ。でもその直径は、 肉眼でギリギリ見える程の細さにまで絞れる。もしもお前が、 あの動作に違和感を覚えていれば、の話だが…」
「──あれは...怯えていたのではなく、刀の落下地点を... そうか、私はやはり侮っていたのか。所詮人間ならば、 死を恐れて当然だと思い上がっていた...」
やがてフォルスの出血が弱まり、その巨体が轟音を立てて倒れる。
それと同時に、 少女二人を拘束していた光の格子がゆっくりと地に降りると、 パキィ!という甲高い音と共に空気に溶けるように消えた。
そこに立っているのは、銀髪赤眼の少女、ただ一人だけだ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。 心より御礼を申し上げます。 技術的に荒削りなところもあると重々存じておりますが、 引き続き少しずつ精進して参ります。
最後に、私からあなたに2つのお約束を。
1つ、私は支援していただけた御恩を、 一生忘れることはございません。
2つ、私は死ぬまで芸術活動をやめません。 私がそれを止める時は私が死ぬ時です。
改めまして、心より深く御礼申し上げます。 本当にありがとうございました。
奈下西こま





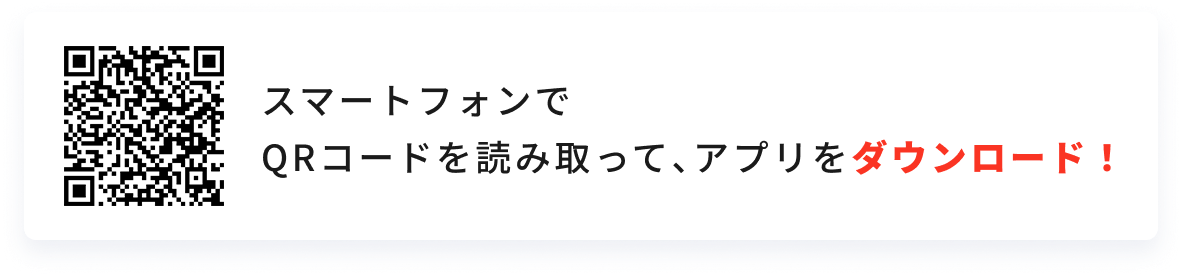


コメント
もっと見る